無動力の歩行支援機『アクシブ』!ロボットスーツと比べて実用性あり?その価格は?
公開日:
:
美容、健康、その他
噂の『アクシブ』を体験してきました!
アクシブとは、
名古屋工業大学の佐野明人教授と今仙技術研究所が共同で開発した
『無動力の歩行支援機』です。
最近、注目の歩行支援機器といえば、
「ロボットスーツ」が有名ですが、
これだと高性能で動力を必要とする分サポート力も強力ですが、
装着に30分程度かかります。
もちろんかなり高額で、個人ではもちろんのこと、
小規模のクリニックや施設などで購入するのも厳しいでしょう。
つまり、現実的に日常使いできるものではありません。
それに対して、アクシブは、
モーターやバッテリーを一切使わず、
「受動歩行」という理論に基づき、
バネと脚の振り子の動きが作用して、
脚の振り出しをアシストするというスグレモノ。
以前、「夢の扉」というテレビ番組で紹介されました。
アクシブの特徴をまとめると、
・シンプルな構造で、本体重量も約550gと軽量。
・モーターがないので、歩行中も静か。
・バッテリーがないので充電不要。
・腰と脚にベルトを2本締めるだけの簡単装着。
・フリーサイズで、3種類のカーボンチューブから選択し脚の長さに合わせるだけ。
腰ベルトは胴囲110cmまで対応可能。
・脚の振り出しのアシスト力は、3段階に調整可能。
・ただし、膝や足首を支える機能はなく、立ち上がりや体重を支える力もないので、
起立や歩行ができない人ができるようになるものではない。
などがあります。
実際にアクシブを装着した感想は、
確かに軽量なのでほとんど機器の重さは感じませんでした。
それに、あまりかさばらないので椅子に腰掛けて装着することができます。
ただし、私は健常者なので、
明確なアシスト力を感じるには、3段階のうち最強レベルの3が必要でした。
もちろん、実際に脚の機能(筋力や持久力)が低下している方は、
感じ方が異なると思います。
そして一般的には、
一方のベルトは膝下に装着するようですが、
これだと前方への脚の振り出しやすさはありますが、
脚全体を持ち上げるような感じはありません。
そこで、ベルトを膝上(太ももの末端部)に装着してみると、
前方への脚の振り出しやすさに加え、脚全体を持ち上げるような機能があり、
より歩きやすくなりました。
装着したときの見た目が気になる方もいるようですが、
アクシブ本体は黒色なので、黒っぽいズボンを履くと目立ちません。
気になる価格は、18万円(税別)で、
頑張れば個人でも購入できる価格です。
現在、右脚用と左脚用がありますが、近いうちに両脚用が出るようです。
両脚用が出たら、また体験したいと思います。
スポンサーリンク
関連記事
-

-
2015年春 花粉飛散予測 東日本は大量飛散?対策は?最新治療も
春は『花粉症』の人にはキツイ季節ですよね。 花粉症とは、スギやヒノキなどの花粉が原因で起こるア
-

-
スマホ、ゲーム機、パソコン、テレビは睡眠や概日リズムに悪影響!就寝前の電子書籍も注意!
スマホなどの携帯電子端末やゲーム機、パソコン、液晶テレビなど に用いられる波長の短い光(ブルーライ
-

-
これまでの常識を覆す変形性股関節症の最新治療法とは?『貧乏ゆすり』で軟骨再生?最大限の効果を引き出す方法は?まずはチェックリストで早期発見!
よく「老化は下半身から始まる」といわれます。 そして、下半身から始まった病気が原因で日常生活も
-

-
男性更年期障害LOH症候群の原因は加齢やディレーラー・ストレス?症状や治療法は?
男性の更年期障害『LOH症候群』(加齢男性性腺機能低下症候群) というものをご存じでしょうか?
-
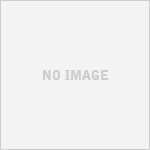
-
ナイスガイシンドロームを克服するには自分と向き合うことから
前回、日本ではあまり聞き慣れない『ナイスガイシンドローム』についてご紹介しました。 これが長く
-

-
1日3~4杯のコーヒーでがんや糖尿病を予防!妊婦の目安は? コピ・ルアクとは?
コーヒーをよく飲む人は、 ある病気にかかりにくい というのが最近話題になっています。 ある
-

-
古代インド発祥のヨガで心臓病リスクを改善!有酸素運動と同じ効果の可能性
古代インド発祥の修行法である『ヨガ』は、 健康意識の高い人を中心に世界中に広がっていますが、 そ
-

-
平均寿命や健康寿命は延伸!高齢者の身体機能・認知機能も向上!でもクルマの運転能力には足りない!
最近、頻発している高齢ドライバーによる悲惨な交通事故。 人間の命の大切さには年齢は関係ありませ
-

-
中高年の男性は要注意!『LOH症候群』とは?その対策は・・・?
加齢による多様な身体の変化やストレスにより、 男性にも『更年期障害』があることは知られています
-

-
地中海食でテロメアを長くして健康増進や長寿も
近年、『地中海食』が注目されていますね。 理由は、地中海沿岸諸国では、イギリスやドイツ、北欧な







