やる気やモチベーションを引き出すコツは?しゃべる、手を使う、歩く、簡単な行為で脳のウォーミングアップ
公開日:
:
美容、健康、その他
新たな年度がはじまる4月。
学生や社会人の皆さんは、
慣れない環境に適応しようと頑張っているのではないでしょうか?
しかし残念ながら、頑張っているからといって必ずしも結果が出るとは限りません。
すると、かなりの意気込みをもって取り組み始めたことでも、
次第にやる気がなくなり、ますます結果が出にくくなってきたりします。
そして、その良くない状況をどうにかしなければならないとわかってはいるものの、
どうにもならない状況に陥ってしまったりするものです。
そんなとき、どうやって『やる気、モチベーション』を取り戻すとよいのでしょうか?
人間はモチベーションがあってはじめて前に進むことができるし、
やる気が湧くからこそ自分の持てる力を仕事や生活に役立てようとします。
しかしながら難しいのは、
「やる気はメンタリティに大きく左右される」ということ。
気分が沈めばやる気は出ないし、
逆に気が張っていれば、体中から無尽蔵のごとく湧いてくるものです。
これを自分自身で意識的にコントロールできれば、こんなに心強いことはありません。
実は、この「やる気」をコントロールするコツがあるのです。
例えば、
アスリートが競技の前にウォーミングアップするのと同じように、
脳も回転数を上げるための準備運動を行えば、
やる気は高まっていきます。
何をすればよいかというと、
「しゃべる」、「手を使う」、「歩く」
といったごく簡単な行為です。
口や手、足を動かすという行為は、
脳領域の「運動系」と呼ばれる機能を使うことになります。
実は、 「やる気」と「運動」は密接に繋がっている のです。
人間の脳の発達について考えてみると、
生まれた赤ん坊が二足歩行ができるようになり、
手足を自由に操れるようになり、
口を使って言葉を話せるようになってはじめて、
高度な思考力も発達していきます。
日常生活も同じで、
運動系を十分に動かしておくことが、
思考力やモチベーションの活性化に有効なのです。
つまり、モチベーションを高めるために、
日常生活において「脳の運動系を刺激する習慣」を持つとよいのです。
具体的には、
○ウォーキング
○部屋の片付け
○音読
などがあります。
脳生理学的にみると、
運動系の機能は脳の表面中央付近に分布していて、
その脳領域を働かせることは、その領域に至る脳の血流をよくすることを意味しています。
特に足を動かすための機能は、
頭頂部(頭のてっぺん)に近い部分が担っているので、
ウォーキングをすることで血液が脳の高いところまで行き渡り、
結果的に脳全体にも血液が循環しやすくなります。
部屋の片付けは手の運動であると同時に、
前頭部が司る選択・判断の機能を強化する行為になります。
音読は、単に口を動かすだけでなく、耳を使い情報を取得することで、
脳の入力 ⇒ 情報処理 ⇒ 出力
という要素が連続的に含まれているので、適度な脳の刺激に向いています。
さらにこれらの行為は、感情や理性、創造、やる気や行動力など、
人間の精神活動に欠かせない大脳辺縁系や前頭連合野を繋ぐ、「報酬系」も刺激します。
「報酬系」とは、
人間の脳において、欲求が満たされたとき、
あるいは満たされることが分かったときに活性化し、
その個体に快の感覚を与える神経系のことで、
別名『A10神経』とも呼ばれています。
つまり、ウォーキング、部屋の片付け、音読などは、
脳全体の活性化を促すので、
モチベーションを高めるウォーミングアップに最適
というわけです。
また、これらの行為が「単純」であることもポイントの1つです。
アスリートがウォーミングアップを行う際には、
軽いランニングやストレッチなど簡単な動作から始め、
決して複雑・高度な動作から行うことはありません。
脳も簡単なことから始めることが大事で、
複雑・高度なことから始めると頭が適応できません。
複雑なことにトライして失敗すると、
ウォーミングアップ効果が得られないばかりでなく、
ネガティブな気持ちに陥る危険性があり、
これでは本末転倒ということになりかねません。
簡単な作業を通じて成功体験を積めば思考はポジティブになり、
やる気も引き起こされます。
ただし、やる気があっても成果が伴わないケース、
つまりモチベーションが空回りしている場合もあります。
こういったときは、
やるべきことを「着実にできること」から仕切り直すことが大切です。
例えていうと、
「ホームランからヒット狙い」に気持ちを切り替えれば、
意外に事はスムーズに運びます。
一方、気が散って集中できなかったり、物事に飽きを感じたときは、
「制限時間」を設けるのが効果的です。
先を決めれば段取り良く仕事を進めるようになり、
目的に向かいモチベーションも集中力も高まります。
制限時間を設ける際は、
一度に全部をこなすのではなく、
数回に分けて片付けるなど、
細切れに行うのも重要なポイントです。
「休憩も挟みながらコツコツやっていく」ほうがやる気を維持しやすく、効果的でもあります。
新たな年度はまだ始まったばかり。
うまくいっていないことも、これからどうにでも軌道修正できるはずです。
スタートラインに立ったときの「やる気」を取り戻し、充実した日々を送りましょう!
潜在意識を書き換えて幸せな人生を自分で築く!についてはコチラ↓↓↓
http://challenge-tt.xsrv.jp/519.html
食事、運動、休養、睡眠など規則正しい生活が脳機能をよい状態にする!についてはコチラ↓↓↓
http://challenge-tt.xsrv.jp/324.html
スポンサーリンク
関連記事
-

-
砂糖への課税は国民の健康対策として有効か?加糖飲料を減らせば糖尿病リスクが大幅に減る!
『国民の健康対策として、たばこ、アルコール、砂糖などへの課税強化を求める』 厚生労働省の有識者
-

-
糖尿病は認知症と関連あり!記憶を司る海馬への影響は?最近注目の筋膜リリースは糖尿病にも効果がある?
現代社会において、『糖尿病』と『認知症』という疾患名 を耳にする機会は大変多くなっています。
-

-
座っている時間が長いと体に悪い?がん、糖尿病、心臓病のリスクが高い?デスクワークが多い人の対策は?
やはり、「座っている時間が長いと体に良くない?」というのは、 どうやら本当のようですね。 以
-

-
地中海食でテロメアを長くして健康増進や長寿も
近年、『地中海食』が注目されていますね。 理由は、地中海沿岸諸国では、イギリスやドイツ、北欧な
-

-
薄毛、抜け毛対策は?食事は?運動は?睡眠は?「髪と頭皮」の関係は「植物と土」の関係?
年々増加している薄毛や抜け毛などの髪の悩みは、 中高年の男性に限らず、今や若い世代や女性にまで広が
-

-
超ヘルシーなイスラム・中東の伝統料理フムス
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、 イスラムの戒律で認められたものであることを
-
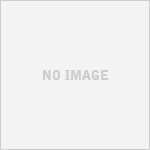
-
気になる加齢臭を撃退するには食事・運動・清潔が重要!
以前、老化度のチェックをしましたが、老化が原因とされるものに『加齢臭』があります。 加齢臭は、
-

-
シワ取りやワキガ、脳卒中の後遺症にも行われるボツリヌス菌治療の最新治療法は?心房細動に効果!
みなさんは 『ボツリヌス菌』 というものをご存知ですか? 「地球最強の毒素」を産生
-

-
中高年の男性は要注意!『LOH症候群』とは?その対策は・・・?
加齢による多様な身体の変化やストレスにより、 男性にも『更年期障害』があることは知られています
-

-
日本人の13人に1人がうつ病を経験!セルフチェックで早期発見・早期治療!
現代社会が「ストレス社会」といわれるようになって久しいですが、このストレスによってさまざまな心身の不





